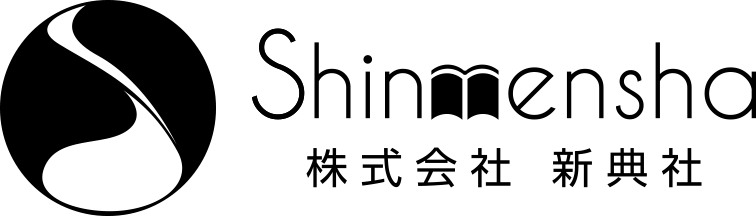説明
目次
序言
第一章 文芸学における作品への問い―学としての意義―
第二章 一般文芸学の可能性―岡崎義恵の史的文芸学と時間性―
第三章 文芸学における言の時間性―「直観」「継起」を始点として―
第四章 文芸学における価値認識―歴史美学的考察―
第五章 素描 岡崎義恵『日本文芸学』の周辺
第六章 菅原道真「雨夜」について―『菅家後集』の悲憤―
第七章 『古今和歌集』以後と言語の自立性―八代集の主体「われ」「わが」の領域―
第八章 平安仮名文芸の基層としての語らい―〈歌語り〉を包摂するもの―
第九章 「打聞き」の系譜―『枕草子』を起点として―
第十章 『枕草子』の赤き薄様―典型の表現と連想―
第十一章 『枕草子』の「雨」―「心ときめきするもの」として―
第十二章 『枕草子』の香りと信仰―樒の香の尊き―
第十三章 したわらびこそ―平安文芸の食と趣向―
第十四章 『源氏物語』王権論批判―栄耀無常運命有限―
第十五章 宇治 須磨明石 「水の男」―「水の女」の再検討のために―
第十六章 『源氏物語』の梗概と時間性―作品の時間性の定位―
第十七章 『源氏物語』『枕草子』とその時代―紫式部と藤原道長との交流から―
第十八章 詩史の時期区分と批評主体―大江匡房「詩境記」からの展望―
第十九章 平安文芸史素描―言語分節と時間性―
初出
後記 その一
後記 その二